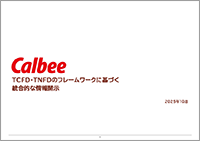未来につなぐ自然資本
TCFD・TNFD提言に沿った情報開示
基本的な考え方
生物多様性の損失を止め、反転させる「ネイチャーポジティブ」という考え方が世界で広まっています。日本においても、生物多様性の保全に積極的な企業に資金が流れる仕組みを構築するために、「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」が環境省、農林水産省、経済産業省、国土交通省の4省連名で、2024年3月に発表されました。この戦略の中で、「ネイチャーポジティブ経済」実現のためには、民間企業が自然保全の取り組みを推進・開示し、その内容について消費者や市場等から評価を受け、取り組みが進む社会へと変化することが重要だとされています。
私たちカルビーグループを含め、すべての企業の活動は何らかの形で自然資本が生み出す生態系サービスに依存し、同時に自然に対してインパクトを与えています。そのため、生物多様性の損失は事業の継続不能に直結する重大なリスクとなります。生物多様性の損失を防ぎ、回復に向かうためには、生態系の保全・再生に加え、気候変動への対策、持続可能な生産や消費削減に取り組むことが不可欠です。
こうした背景から、カルビーグループではこれまで開示していたTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)に加え、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)のフレームワークに基づき、自然資本への依存とインパクト、リスクと機会に関する統合的な開示を行いました。今後も社会環境の変化を適切にとらえながら、取り組み内容のさらなる充実と改善を重ね、持続可能な地球環境の実現を目指します。
TNFD開示推奨14項目との接合
| 大項目 | 小項目 | 本開示における対応箇所 |
|---|---|---|
| ガバナンス | A. 自然関連の依存、インパクト、リスク、機会に関する取締役会の監督について説明する |
|
| B. 自然関連の依存、インパクト、リスク、機会の評価と管理における経営者の役割について説明する |
|
|
| C. 自然関連の依存、インパクト、リスク、機会に対する組織の評価と対応において、先住民族、地域社会、影響を受けるステークホルダー、その他のステークホルダーに関する組織の人権方針とエンゲージメント活動、および取締役会と経営陣による監督について説明する |
|
|
| 戦略 | A. 組織が短期、中期、長期にわたって特定した、自然関連の依存、インパクト、リスク、機会について説明する |
|
| B. 自然関連の依存、インパクト、リスク、機会が、組織のビジネスモデル、バリューチェーン、戦略、財務計画に与えた影響、および移行計画や分析について説明する |
|
|
| C. 自然関連のリスクと機会に対する組織の戦略のレジリエンスについて、さまざまなシナリオを考慮して説明する |
|
|
| D. 組織の直接操業において、および可能な場合は優先地域に関する基準を満たす上流と下流のバリューチェーンにおいて、資産や活動がある場所を開示する |
|
|
| リスクと インパクトの管理 |
A.(ⅰ)直接操業における自然関連の依存、インパクト、リスク、機会を特定し、評価し、優先付けするための組織プロセスを説明する | (今後対応を検討) |
| A.(ⅱ)上流と下流のバリューチェーンにおける自然関連の依存、インパクト、リスク、機会を特定し、評価し、優先付けするための組織のプロセスを説明する | (今後対応を検討) | |
| B. 自然関連の依存、インパクト、リスク、機会を管理するための組織のプロセスを説明する |
|
|
| C. 自然関連リスクの特定、評価、管理のプロセスが、組織全体のリスク管理にどのように組み込まれているかについて説明する | ・リスクマネジメント体制(⇒P.18)(別ウインドウで開く) | |
| 測定指標と ターゲット |
A. 組織が戦略およびリスク管理プロセスに沿って、重大な自然関連リスクと機会を評価し、管理するために使用している測定指標を開示する |
|
| B. 自然に対する依存とインパクトを評価し、管理するために組織が使用する測定指標を開示する |
|
|
| C. 組織が自然関連の依存、インパクト、リスク、機会を管理するために使用するターゲットと目標、それらと照合した組織パフォーマンスを記載する |
|
TCFD開示推奨11項目との接合
| 大項目 | 小項目 | 本開示における対応箇所 |
|---|---|---|
| ガバナンス | A. 気候関連のリスク及び機会についての、取締役会による監督体制を説明する |
|
| B. 気候関連のリスク及び機会を評価・管理する上での経営者の役割を説明する |
|
|
| 戦略 | A. 組織が識別した、短期・中期・長期の気候関連のリスク及び機会を説明する |
|
| B. 気候関連のリスク及び機会が組織のビジネス・戦略・財務計画に及ぼす影響を説明する |
|
|
| C. 2℃以下シナリオを含む、さまざまな気候関連シナリオに基づく検討を踏まえて、組織の戦略のレジリエンスについて説明する |
|
|
| リスクと インパクトの管理 |
A. 組織が気候関連リスクを識別・評価するプロセスを説明する |
|
| B. 組織が気候関連リスクを管理するプロセスを説明する |
|
|
| C. 組織が気候関連リスクを識別・評価・管理するプロセスが組織の総合的リスク管理にどのように統合されているかについて説明する |
|
|
| 測定指標と ターゲット |
A. 組織が、自らの戦略とリスク管理プロセスに即して、気候関連のリスク及び機会を評価する際に用いる指標を開示する |
|
| B. Scope1、Scope2及び当てはまる場合はScope3の温室効果ガス(GHG)排出量と、その関連リスクについて開示する |
|
|
| C. 組織が気候関連リスク及び機会を管理するために用いる目標、及び目標に対する実績について説明する |
|